【開催報告】シンポジウム「鹿児島で北東アジアを考える」
2019年12月21日(土)に鹿児島大学でシンポジウム「鹿児島で北東アジアを考える」が開催されました。本シンポジウムは、人間文化研究機構ネットワーク型基幹研究プロジェクト「北東アジア地域研究推進事業」北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター拠点と鹿児島大学国際島嶼教育研究センターとの共催で企画・組織されたものです。
鹿児島は歴史的にのゲートウェイとして、アジア諸国だけでなくヨーロッパにまで開かれていました。このような「海」を介した交流という視点を念頭におきながら、北東アジアを考えてみよう、というのが本企画のコンセプトの一つでした。
 |
 |
第一セッションは、「北東アジアの国際関係:歴史、理論、比較」というテーマで専門地域の異なる3名の研究者に報告をしていただきました。金成浩(琉球大学)による報告「北東アジア冷戦構造の変容と北朝鮮」は、民間レベルの国際交流にも影響を与えている北朝鮮の核開発問題について、その淵源を考察する試みでした。具体的には、1980年代末から1990年代初頭にかけてのクロス承認問題をめぐる、韓国、北朝鮮、ソ連、日本、中国の政策決定過程を検証し、北朝鮮の核開発の起点については諸説ありまだ明らかにされていないが、ソ連による一方的な切り捨てを始めとする1980年代の国際関係の構造的変化が北朝鮮の核開発を加速化させてことは確かであろうと結論しました。
佐橋亮(東京大学)による報告「北東アジアの安全保障秩序:米中関係と米同盟ネットワークの相互作用」では、戦後アジアの秩序に注目し、その形成と現在までの変容について取り上げました。東アジアでは、イヴェリン・ゴーが指摘するように、1970年代に米中が接近することによって地域の平和の基盤が達成されました。しかし佐橋報告によると、実は1950年代からアメリカと中国の間には戦争を回避するという共通の目標がありました(共有はせず)。つまり、日米同盟の安定の一方で、朝鮮戦争後、米中が戦争を回避してきたことがこの地域の平和の基盤だったのではないかという見方を提示しました。そして、過去30年間の日米中の三角関係の変化を論じたうえで、現在は米中対立の局面に入り、日本は日米関係を維持しつつ過去2年間で日中関係を改善してきたものの、地域の安定にどの程度貢献できるかは疑問である。戦後アジアの地域の安定が維持されていたのは、中国がアメリカの同盟(ネットワーク)を認めていたためであり、今後この基盤が崩れてしまえば、地域秩序は相当不安定化するのではないかという見方を示しました。
宮脇昇(立命館大学)による報告「地域対話におけるモンゴルの役割:欧州の経験から」では、政治体制や経済体制の違いを超えて、加盟国間でヘルシンキ宣言に盛り込まれた10原則を共有し守って行こうという欧州安全保障協力機構(OSCE)の成り立ちと、中立政策をとる諸国のブロック「N+N」がCSCE/OSCEの発展に果たした役割について説明しました。そして冷戦終結後の北東アジアにおいて、「新しいヘルシンキ」を目指すモンゴルの役割について、同国がイニシアチブをとる「ウランバートル対話」を事例に検討しました。
コメンテーターの尾崎孝宏(鹿児島大学)からは、北東アジアの安全保障を北朝鮮イシューとして見た場合にはモンゴルは地政学的に重要な役割を果たしうるが、中国イシューとしてみた場合、モンゴルの存在感は小さくなるのではないかという疑問が出されました。同じくコメンテーターの益尾知佐子(九州大学)は、日本と中国、それ以外の国々の間でも政治、安保面の対立を抱えていても経済は維持するというコンセンサスがあるのではないか、この地域における秩序を考える場合、経済ファクターをもっと考慮すべきではないかという点を指摘しました。
 |
 |
第二セッションは「島と海:アジアと欧州の比較」というテーマで、それぞれキプロス、奄美、欝陵島をフィールドとする3人の研究者が報告を行いました。伊藤頌文(慶應義塾大学)は「分断のキプロス:紛争と統合の狭間」と題して、ヨーロッパで最も「凍結された」民族紛争と呼ばれる、キプロス島の分断問題を取り上げました。キプロスは、1974年の紛争でトルコが軍事侵攻し、多数派のギリシャ系住民が住む南部「キプロス共和国」(*EU加盟)と少数派のトルコ系住民が住む北部「北キプロス・トルコ共和国」(*1983年に独立宣言。トルコのみが承認。)の分断が固定化しました。キプロス紛争を題材とする平和構築論は、再統合=平和回復という文脈で論じられる傾向にあるのに対し、伊藤報告は南北間の人や車両の往来がかなり自由化されていること、島内5カ所のクロスポイントが機能し、むしろ名所として観光化されている内実を取り上げ、「分断による平和」という現在のキプロス島の実態を直視した上で平和について考える必要があることを指摘しました。
平井一臣(鹿児島大学)は、「島尾敏雄のヤポネシア論再考」というテーマで、戦後約20年間奄美で生活して創作活動を行った作家・島尾敏雄のヤポネシア論や琉球弧論について、これらが形成された1960年代から70年代にかけての日本の政治社会状況との関係から再考しました。島尾のヤポネシア論は1961年に発表されていますが、当初から柳田國男の南島論の強い影響下にあることが指摘されており、南島に日本の源郷を見いだそうとする南島イデオロギーを代表するものとして扱われてきました。この点に関して、平井報告は、当初生活者の視点から奄美を理解したいと発言していた島尾は、奄美の本土復帰後の急激な開発とそれによる奄美社会の変化のなかで、決意に揺らぎが生じ、むしろ奄美を理解することの難しさから、生活者としての奄美理解を断念していたため、ヤポネシア論を深めていくことができなかったのではないか、という見方を示しました。そして学術的な装いをまとったヤポネシア論から離れて、ヤポネシア論の失われた可能性を再考する必要性を訴えました。
福原裕二(島根県立大学)は、「竹島/独島の属島と化される欝陵島」というテーマで、日本と韓国の係争地である竹島/独島にもっとも近い有人島である欝陵島(ウルルンド)の変化について、フィールドワークと統計データに基づいた報告を行いました。欝陵島で住民登録をしている人数は2017年現在10,123人(実際の今日中社は8,000人程度と見られる)であり、実質的に韓国の人々が生活を営む空間としては最東端に位置する離島です。この島は従来スルメイカ漁と農業で知られており、現在は観光が産業の中心となっています。欝陵島が「国境の島」として意識され始めたのは朴正煕政権下で開発が始まった時でした。その後大きな転機を迎えたのが、2005年に島根県議会が「竹島の日」を制定し、日韓間で竹島/独島問題が先鋭化した時期です。これ以降、欝陵島では韓国政府によって「独島教育、啓発」のための観光地化が推進され、竹島/独島の属島化が進められました。福原は、このような現状の問題点として、属島化によって欝陵島への資金や資材の投下は著しいが、従来からこの島で発展してきた産業にその恩恵が及んでいないこと、このような政府や道による政策が、地元住民の意向を問うことなく進められているのではないか、という問題を提起しました。
コメンテーターの上原良子(フェリス女学院大学)は、海洋に浮かび、大国に囲まれた島の政治をどう分析すべきかという点に関して、ヨーロッパの「内海」としての地中海研究との比較の観点から、三つの分析視角を提示しました。一つは、島の外交力や政治的したたかさ、あるいは独自のイニシアチブに注目する方法、二点目として、経済成長と地域のアイデンティティの変化の関わりに着目してみるやり方、また三点目として、他者が抱く「地中海」や「南の島々」へのエキゾチックでロマンチックなイメージと、島の内部の実態の違いの差異が、何らかのボーダー(境界)を形成しているのではないか、という視点を挙げました。もう一人の討論者である堀江典生(富山大学)は、位置する地域、島の規模、属性が大きく異なるキプロス、奄美、欝陵島を比較する上で、島のランドスケープ(物理的構成要素の集合体。それは利害関係者により空間認識され、意味付けされる)、外部利害関係者、島の「根っこ」、の三要素の相互作用に着目すると、島嶼の境界性の特徴がより分かりやすくなるのではないか、とコメントしました。
 |
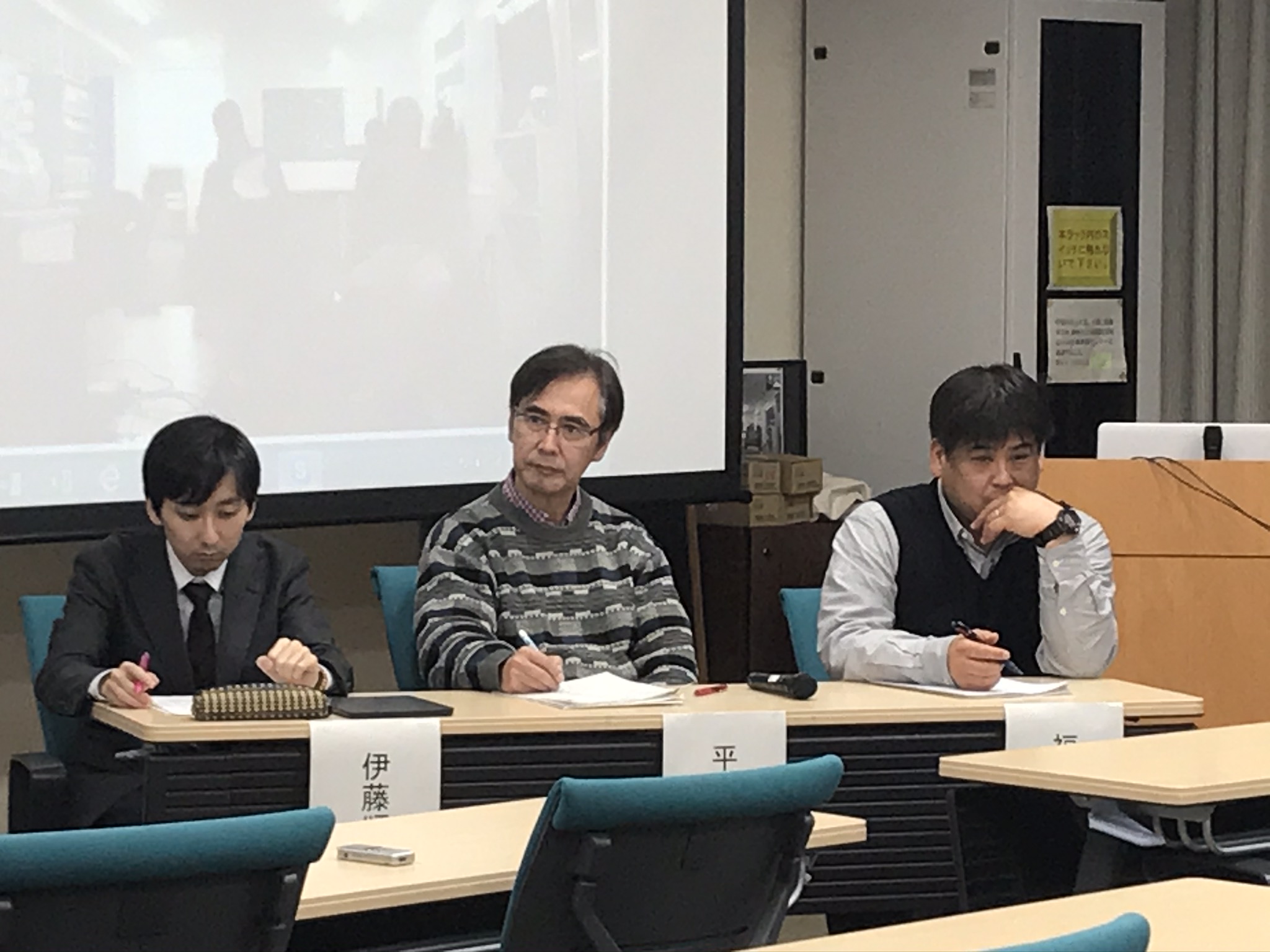 |
今回のシンポジウムでは、北東アジアの地域秩序を大国間関係で捉えるか、それとも経済などの要素を考慮してより多様なアクターによって構成されるものと見なすべきか、また海域アジアと島嶼の役割を視野に入れた時、どのような分析視角が有効かなど、創造性の高い議論が展開されました。国際島嶼教育研究センター奄美分室へ同時中継され、奄美分室から参加してくださった聴講者からは質問もいただきました。シンポジウム全体の参加者は約50名でした。(加藤)



